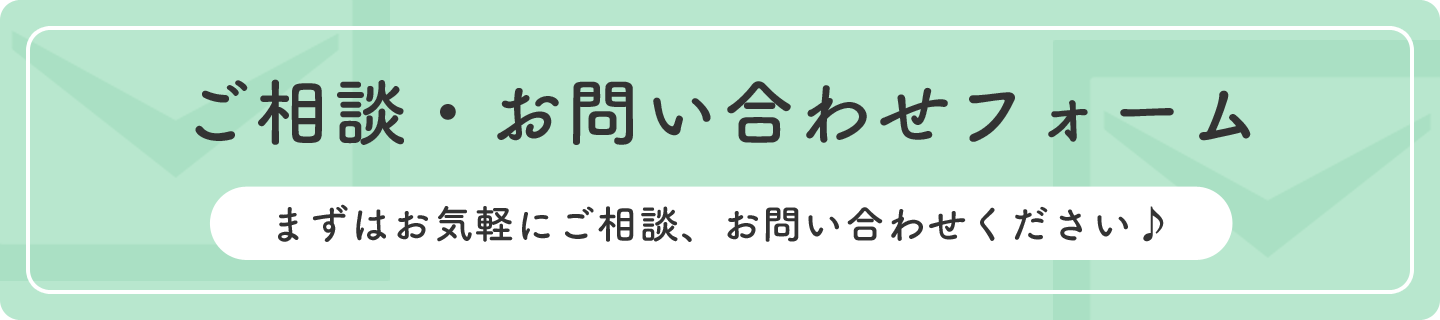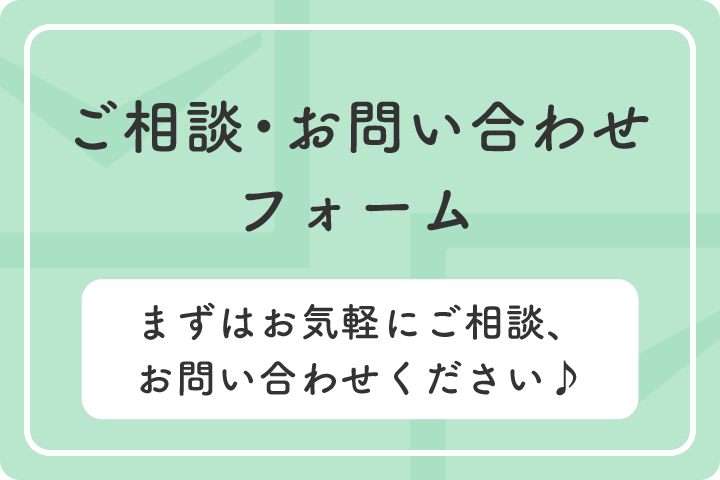解決志向の親和性の高さ
現在行っているリーダーシップ研修には様々な職種や年齢の方々が参加しています。
研修で解決志向や心理的安全性を行っていると、それぞれ自分の置かれた環境や役割に紐づいて落とし込むことになり、振り返りを読んでいてそれがとても興味深いと感じています。
例えば、医療安全管理業務を担っている看護師の方。子供の野球チームのコーチ。子育て中の方。部下のマネジメントに悩みを抱えている方々…等、様々です。
解決志向の親和性の高さ、つまり人に対してポジティブな視点で光を当てるマネジメント、コミュニケーションは優しい平和な世界に繋がるとその力を感じている今日この頃。
「解決志向的生き方したい。する!」と、心に決めて約4年。発展途上中ですが、確実に優しく平和な世界を作っている手ごたえを感じています。
9月に実施した研修の振り返りを一部ご紹介します。
●「こわれたものを直そうとしない」という捉え方。研修を受けるようになってから、問題を抱えているスタッフに対して「きっと何か理由があるんだろう」「その人には、その人の考え方があるんだろう」と、思い接するようになり自分自身も考え方に変化がありました。
●インシデントが発生すると「何が悪かったか」という問題志向で原因を徹底的に追求し「壊れた部分」を探し出すことに注力してきました。今回の研修で示された「こわれたものを直そうとしない」は、エラーをした当事者を「直すべき欠陥(壊れた存在)」と、捉えるのではなく、「理由があってその行動に至った」として当事者を尊重する姿勢の重要性を学べました。
2000年以前の医療安全では「個人の責任追及」が主であったが、現在は「チームや組織全体のあり方を改善しないと防げない」という考えにシフトしているので、この考えは医療安全システム改善へと繋がる組織風土の醸成に不可欠だと思いました。
●オスカーモデルはリハビリを行う際の利用者さんとの目標設定を決める時にも有効ではないかと思いました。
●関係構築に必要な(言葉の理解)が印象に残りました。『相手なりに理解はしているけど、自分の伝えたかったことと相違がある可能性がある』このことを考えながら会話していきたい。
●言葉の理解に関しては、伝えたのにフィルターがかかり間違って伝わっていたことがありました。 業務中での口頭指示もありインシデント・アクシデント回避のため、話し手受け手の双方にこの認識が必要だと思いました。